ほんとに偶然ですが修理が立て込んでいます。
ダルトン扇風機の修理が終わった日に電話が(゚Д゚;)
「HDDレコーダーのが修理できるだろうか?」と
持ち込まれたのは、電気えんぴつ削りを引き渡した翌日であります。
東芝 RD-W301、左の口:VHS で 右の口:DVD
+HDDレコーダー の三位一体型であります。
さすがにBlu-ray対応ではないですが
DVカメラ(デジタルビデオ・カメラ)用のDV端子も!
今どきのビデオカメラは、全てデジタルですが
DVは、デジタル記録方式として最初に世に出た規格ですね~
今どきのは、廃止されている
・D1/D2/D3/D4端子
・スカパー連動端子(スカパーチューナーと直結して制御できる)
・電話回線
これ以上のアナログ・デジタル混在は、ないでしょう!
まるでAV端子の博物館(゚Д゚;)
至れり尽くせりの大変貴重なモデルですね~
まだまだ頑張っていただきたいので、修理も頑張ります(^^)
<症状>
・起動後[HDD]モードのままにしていると
突然電源OFFになって[WAIT]表示になり起動しなくなる。
・起動したらすぐに[HDD]モードから
[VTR]や[DVD]モードに切り替えると
問題なく動作する場合が多い。
持ち込まれた時は、調子が良かったようで、
正常に起動して、HDDに記録された映像が観れました。
一旦、電源OFFしてからは「WAIT」表示から先に進まなくなったような。
「HDD」モードで突然電源OFFということは
HDDが劣化している可能性が最も高いので
事前に換装手順を調べておきました。
Panasonic DIGAでは、
事前に新規HDDの特定セクタにデータを書いておく必要があったけど
この東芝のは、だた、差し替えて、
最初に電源ボタン長押しでRESETして、
HDD初期化に進めばいいらしい。とのこと。
いきなりですが
乗せ換えたショットから(^^ゞ
それにしても
稼働時のHDDの振動音を静音化するインシュレーターが半端ない( ゚Д゚)
まず、ブラケット金具に取り付ける赤丸部に豪勢なゴムのインシュレーター
更にそれを本体に取り付ける所(青丸)にも同じものが!
前モデルでHDDの稼働音が煩いというクレームが多かったのかな~?
そのオリジナルのは、
Seagate ST3300820SCE 300GB 7200RPM
後で気づくに SATA150でした。
TOSHIBA DT01ACA050 500GB 7200RPM SATA600を
これが、出ました!
次は、[HDD/ディスク管理]に行って
[HDD初期化(全削除)]します。
なかなかしつこいですね~
換装テストに使っております。
300GB以上をつけても、録画可能時間は長くならないとのこと。
CrystalDiskInfo Ver.9.1.1では、これ
使用時間:9463時間!だいぶ使い込んだ状態ですので、
ちょっと換装テストに使うだけです。
換装に成功したら、新品を注文する予定であります。
RD-W301には、新品状態だと思わせるため
Windows10のDiskpartで
PartitionなしのUn-Format状態にします。
横道にそれますが
CrystalDiskInfoでは、500.1GB
上のDiskpartでは、465GB
Windows10のディスクの管理では、465.76GB
今回の用途には、支障ないですが、なんでだろう?
所が、電源ボタン長押しでRESETしても
[WAIT]表示になったままで起動しないのです。
HDDを元のに戻しても起動しなくなり
持ち込んだ時よりも悪化してしまいました(@_@)
AC電源コード抜いて~
しばし頭を冷やして、もう一度やってみようと
また元のHDDを外したり~
東芝のHDDを再度Windows10のDiskpartでCleanして
また着けたり~
先に言っておきますが
換装の秘訣①・・・「焦らずに待つ」であります(^^ゞ
AC電源コードを挿して
前面のLCDパネルの表示が[WAIT]のまま変化しません。
通常は、1分ほどで[WAIT]表示が変化しますが
換装後、初の電源入れは、2分ほど待った方がいいでしょう。
実は、最初、こんなに起動が遅いとは知らず、惑わされました。
今度は、根気よく1分ほど待ってると~
[WAIT]⇒[0:00]に変わって点滅しています!
今度は、電源ボタンを押すと
緑に変わり、また[WAIT]
でも、VTRのギアとかが微妙に動いてて
起動シーケンスを進めているのです。
30秒ほど経つと
おっ![00 00 00]に変わったぞ!更にじ~っと待ってると~
出ました!
[了解]したいのですが
リモコンのボタンが反応しません。
右上に「読込み中」と矢印がクルクル回っていて
どうやら、これが終わらないとダメらしい
前面パネルには[ALERT]と表示されています。
1分弱だったか待ってると、右上の「読込み中」矢印がクルクルが消え
リモコンの[決定]ボタンを押すと
前面パネルは、こうなっております。
[時刻設定]に行くと
これが初期状態の様子、現在の日時を入力して
「0:3:54」は、設計者のみぞ知る秘密の時間かな?
当然[開始]
前にここまでたどり着いたことはあったのですが
100%まで行かないところで、突然電源が落ちたこともあり
突然、真っ青に!
まるでWindowsのブルーバック(゚Д゚;)
初期化は、成功したもようで、ひと安心(^^)
反応して、この画面が出ました!
リモコンの[クイックメニュー]で
リモコンの[見るナビ]ボタンを押すと
やっと、換装成功であります\(^o^)/
換装の秘訣②・・・
「HDDは、AC電源コードを5分ほど抜いた状態で交換すること」
素早く交換すると、以前の状態が一部残っている様で
電源ボタン長押しでRESETしても、HDD交換のメッセージがでないことも。
[ディスク情報]を出すと
元の300GBのは、不調だったのでショットがありません。
500GBにしてるので、ちょっとだけ期待したのですが
調べると、元の300GBと同じで、録画可能時間は増えていません。
このレコーダー、起動がメチャクチャ遅いんです。
前面パネルに[WAIT]が出てる時間が長く
画面が出ても、[読み込み中、矢印クルクル]が続くし
次に進む前に、起動の様子を記録しておきます。
**********
< 初回起動 >
AC電源コードを抜いた保管状態から、AC電源コードを挿して、初めての起動
0 :
ACコードを挿すと[WAIT]が続く。まだ電源ボタンは、操作不可。
60秒後: 時刻表示になり、電源ボタン押下で赤⇒緑点灯、また[WAIT]表示になる。
その後は、下記の通常起動と同じです。
< 通常起動 >
AC電源コードを挿した状態(時刻が表示されている)からの起動
0 : 電源押下で赤⇒緑点灯、[WAIT]表示が続く。
2秒後: [WAIT]表示の横の[〇]が消える
30秒後: カウンターが[00.00.00]になる
34秒後: 画面にRDロゴが一瞬出る
37秒後:
画面右上に[読込み中]表示、小さな矢印がグルグル回りだす
39秒後:
地デジ映像が出るが、右上[読込み中]まだ消えず
70秒後:
[読込み中]が消え、スタートメニューが出て、リモコン操作可能になる。
OFF :
電源ボタン押下で、[終了処理中です]が出て
約3秒後に画面が消え、電源ボタン赤、時刻表示になる
※AC電源コード挿して、2分以上経過しても
[WAIT]⇒[時刻表示]にならない場合は、
換装直後の起動以外だと、故障と診ていいでしょう!
**********
さて、
初期スキャン、地上Dだけにして、地域選択など
幾つかの設定画面を通って
UHF、CATVと進み
当たり前ですが、地デジが映りました!
換装後の初の地デジ
1分弱ですが、録画しました。
修理とは関係ないですが
妙な住所ができたというニュースが録画されてました(@_@)
次は、VHSテープを
依頼者さんが本機を修理したい理由は
古いアナログテープをデジタル化することなので
これが正常にできないと使い物にならないのです。
もはやマーティー工房にあるまともなVHSは、これ1本だけです(^^ゞ
メインメニューから[かんたんダビングする]にすると
矢印の位置を移動させるだけで、
どこからどこへダビングするか設定できるのです。
これは、素晴らしく使い易いですね~(^^)
1年ほど前に「MPEG2 to USB Hardware ENCODER」の
「IO DATA GV-MDVD3」中古¥980で入手できたのまで良かったけど
付属の「DVD MovieWriter 7 Special Edition for I-O DATA」で
MPEG2にデジタル化して~シーン編集して~
更に別のソフトでH.264/MPEG-4 AVCにしたのでありました。
お陰で、暫く腰痛と肩こりに悩まされたのでありました(^^ゞ
工房住人Cの幼稚園の運動会やら
クレヨンしんちゃんやら元祖ドラえもんやらでしたが、
無事、VHS⇒HDDへダビング成功であります\(^o^)/
喜びもつかの間
突然、地デジが映らなくなったのであります(゚Д゚;)
アンテナケーブルは、異状ないし
電源も落ちてないのです(@_@)
「E202」エラーとは、何だ?と
RD-W301の応用編マニュアルを探してると
これが目に入りました!
内蔵電池は、見えないので、DVDドライブの下ですね。
電源コネクタとフラットケーブルが抜けました。
電圧を測ってみます。
このコネクタは、赤部分を両サイド持ち上げるタイプです。
無理に引っ張ってコネクタを破損すると大変な事になります。
写真とってるので、片手ですが
最新の注意を払って、両手の指先を引っ掛けて
黒いバーをそ~っとゆっくり1mm程だったか持ち上げると
フラットケーブルは、スルッと抜けます。
電源コネクタは、ちと硬く嵌っているので
ショートノーズ・プライヤ(通称ラジオペンチ)で
ゆっくり押し出すように引っこ抜きます。
4本の取付ビスを外して
DVDドライブを外しました。
発見!黄丸部の物体が、内蔵電池ですね~
HDDのSATAケーブル、横に避けてもらって
拡大
電圧を測ってみます。
0.1Vってとこですね~
ほぼ完全に放電なさっております。
DVDドライブのラベルです。
SW-9576-E、前面パネルなし、一部改変された東芝専用です。
一般品は、SW-9576-C だそうです。
今はなき、Panasonic Communication Co., Ltd.
福岡市博多区美野島になっています。
もっと昔は、四国の寿製が主流でした。
I/Fは、IDEですね~
もはや、Panasonicサイトには、情報が存在しません(~_~)
I・O DATAのDVR-AM16CVシリーズの中身が同じなので
仕様を拝借させていただきますとm(_ _)m
DVD-RAMの殻付き(カートリッジタイプ)に対応してるんですね~
書換可能で長期保存性が格段に良いDVD-RAMだったのですが
2019年に製造中止になってます(T_T)
さて、内蔵電池、半田付けされていますが、
たかが、内蔵電池交換にメイン基板を外すのは、リスク大なので(^^ゞ
表側から日本製のアングルニッパーで(^^)
電池のスポット溶接された所から剥がします。
PCの内蔵電池としても使われてますが
車のキーレスエントリーリモコンで使うので
たまたま先週、予備を2個買っております(^^)
最短で考えると3年もしたら、また交換するかもしれないので
外部に電池ボックスをつけて、簡単に交換できるようにしたいので
今後の為にも多めに発注しておきます(^^ゞ
では、改造に取り掛かります。
バックパネルの写真中央上の赤点の所に穴を開けたいので
センタポンチ打って~
このセンタポンチツールは、先端を合わせて
後からグ~ッと押すと、内部のバネでバチッと打ってくれるので
この様な金槌が使えない場所には、とても便利です(*^^)v
これです。
執筆時点では、赤と青 417円(10%OFF、送料無料)でした。
約Φ5のシリコンチューブを
もしかして点滴とかに使われてるのと同じかな?
開きました!
穴開け終了!
外側も
リード線を通して~
半田付けの準備して~
半田付け終了!
半田ごての熱で縮めます。
まずは、Φ2のドリルビットで
内側は、切削屑が、基板に落ちないように
ガムテープで防御しております(^^)
次は、Φ4.5で
内側のガムテープを少し剥がすと
切削屑は、全てガムテープで受け止めれたようです。
大きいドリルビットを手回しでバリ取りします。
写真撮って切削屑が落ちてないことを確認しておきます。
シリコンチューブを通します。
思惑通りの挿入硬さです(^^)
リード線は、これ使います。
熱収縮チューブを被せて~
暴れないように、結束バンドでSATAケーブルと束ねます。
結束バンドで留めておきます。
既に電池ボックスは、発注していますが
「地デジの録画」と「VHSテープからの録画」
ほぼ2時間後
[設定の初期化中です]ってのが終わったら
時計は、RESETされてなく
DVDドライブを乗せて
フラットケーブルを挿し込みます。
ここは、しっかり挿し込んでないといけませんので~
写真撮って拡大して確認しておきます。
上の方のとブルーの出方が同等なので、大丈夫ですね(^^)
届くまで、この状態で作業を続けます(^^ゞ
AC電源コードを一旦抜いても
時刻がちゃんと表示されるようになりました。
今更ながら、ここは時計だったのか~と(^^ゞ
「0:00」の時「:」が薄くて見えなかったもので~
これ「12:40」ですが「:」が見えないんですよね~(~_~)
[HDD]モードで地デジを受信して
4時間放置しましたが、異常なしでした\(^o^)/
現在、東芝HDD 500GB、内蔵電池交換後であります。
もしかして、全ての原因は、内蔵電池だったのかも?
内蔵電池が空になって、システムが時刻を必要になって
時計をみると、「時刻がわからな~い(@_@)」と錯乱して
電源OFFしてしまってたのではないだろうか?
これは、元のHDDに戻しても大丈夫かもと
最初の東芝 500GBの時は、これでした。
どうやら、正常にHDD認識された状態で電源OFFして
HDD乗せ換えた場合は、上の表示がでるようです。
HDDの初期化します。
もう何度もやってるので
100%のタイミングを逃さず、パシッ!(^^ゞ
1分ほどですが、異状なくできました(*^^)v
内蔵電池を交換した効果なのか!?
[HDD]選択状態で、地デジを流したままにしてたら
15分ほどだったか
突然、電源OFFになり[WAIT]表示に (゚Д゚;)
幸い、東芝 500GBで異状なく動作していて
元のSeagate 300GBのHDDが逝っても大丈夫なので
SATA to USBでWindows10に接続して診断することにします。
CrystalDiskInfo Ver.9.1.1での診断結果は、これでしたが
これでは判らない何か異常があるのではないだろうか?
Low Level Formatすると
不良セクターを冗長セクターに置き換えてくれるそうなので
Diskpartで「clean all」します。
3~4時間は、かかるだろうし、発熱もするだろうので
上にでかいヒートシンクを乗せて~
SATA to USB アダプターのアクセスランプがチカチカするだけで
Widows10のコマンドプロンプトは、黙ったままなので
ちと不安にはなるのですが
無事に終わりました(^^)
「クリーン」という字を見て
すっかり改善した気分で
また、元のHDD Seagate 300GBをRD-W301に乗せて~
起動したので、今度は[設定を出荷時に戻す]からやってみます。
最後にこれが出て、数秒後に
突然、電源OFFになりました(>_<)
ドキッとしましたが、時刻が表示されていて
電源ボタンを押すと、すぐに緑になって起動が始まりました。
最初にこの画面が出たので
工場出荷状態に戻ったってことですね。
チャンネルの初回スキャンをやるだけでした。
どういうわけか、
ロシア語ウクライナ語なので
発熱が大きいかもなので、放熱板を乗せて~
薄型まな板の切れ端が転がっていました!
2液性なのですが、シリンジも、プランジャーも
接着剤が硬化するまで、ティッシュの箱を代替わりに(^^ゞ
CR2032を装着して
時計用電池ボックスを外付する前に
電源落ちて、VHSのカウンターは、RESETされてるので
6分ほどかかりました。
中央の所、352.87GBの所まで、
ちと気になるので
2回目で良くなっちゃいました(^^)
AC電源コードを挿して、電源ボタン長押しでRESETして
リモコンは、全く反応しないので
再起動すると、さすがにこれが出ますね~
最初に[HDD初期化]していますが
[HDD初期化]しておきます。
41分31秒地点クリア(^^)
RD-W301との接続は、DV端子
挿します。
VTR部と電源ユニットの間の仕切り板を外して
中央下の黄:12V、赤:5Vです。
HDDのフォルダーも初期化されて、この状態なので
メインメニューから[HDD初期化]やれば、
これに戻ります。
このまま、数時間エージングして
突然の電源OFFがないか、様子を見ることしようかな~と
ちょっと[放送切換]を押してみたら、
リモコンが全く反応しなくなりました。
電源ボタン押してもOFFになりません(~_~)
仕方ないので、電源ボタン長押しで強制終了!
起動は、普通に起動したのですが
大谷さんが現れて、この警告が!
前面パネルにも[ALERT]が!
この後、もう一度、
[設定を出荷時に戻す][HDD初期化]しましたが
今度は、[チャンネル]ボタンを押した途端にフリーズ(>_<)
これで、元のHDD Seagate 300GB、NG決定です(T_T)
修理が終わって執筆中にまじまじと分析してみると(^^ゞ
7200RPMなのに、SATA150だったのか~
温度・使用時間は、当然異なるので別として
字が小さくて、数値が読めないので
少し見易くしました(^^ゞ
・シークエラーレート:2D11EC ⇒ 344D09
差は、+73B1D(16進)= 473885(10進)
の変化は、大き過ぎる気がします?
・ハードウェアECC検知エラー回数:6ECEE3E ⇒ 6ED592D
差は、+6AEF(16進)= 27375(10進)
「代替処理済のセクタ数」「代替処理保留中のセクタ数」は、異常なく
変化もしてないですね~
RD-W301では、使えないことになりましたが
どちらも「正常」になってるので
普通のデータ用なら使えるんだろうか?
「シークエラーレート」とは、
・HDD内部の磁気ヘッドに関する情報
・磁気ヘッドの移動(シーク)時にエラーが発生した数値が記録される
この数値が高いとHDDの磁気ヘッドに問題がある可能性がある。
ということです。
そのエラーを「ハードウェアECC」で回避しようとしているが
「ハードウェアECC検知エラー回数」は、回避できなかった回数でしょう。
現在、調子よく動作している東芝 500GB
RD-W301に乗せる前にチェックしたのは、これ
「ハードウェアECC検知エラー回数」の項目は、ありませんが
「シークエラーレート」オール「0」であります。
これが、普通の姿なのでしょう。
長くなりますが、解析が続きます。
CrystalDiskInfo 9.1.1では、S.M.A.R.T.情報のみの表示なので
今回、探して見つけた
14, Oct. 2021 ReleasedのVersion 537を初めて使います。
Chromeで英語に、Braveで日本語に翻訳しました。
S.M.A.R.T.情報は、CrystalDiskInfo Ver.9.1.1と同じなので
まずは、わりと短時間で済む
[Quick surface scan with graph]ってのを
それでも約10分ほどかかりました。
全てじゃなくて飛び飛びでBlock単位のRead Testするようです。
block size:256 なんですね~
SPEEDのグラフは、最後が急に速くなってますが、
特に遅い所は、見当たらないので、良さそうに見えますが
中央の所を拡大すると~
ほとんどが、5msec以内の応答速度ですが
50の所、つまり、20m以上~50msec以内:2
200の所、50m以上~600msec以内:1
これが、異常を起こしてた原因だったようです。
夜中に放置して、3時間かかったようです。
Read Speedのチェックをフル領域でやりました。
全体でみるとSpeedは、問題ない様子ですが
Read Time 200ms以上~600ms未満のブロックが
21個もありました!
前のQuickのグラフもですが、Low Level Format後です。
S.M.A.R.T.情報と合わせると
磁気ヘッドのシーク(移動)時にエラーですね。
元のSeagate 300GBは、ボツ決定したので
また、東芝HDD 500GBに換装して
起動して、地デジが映ることだけ確認して、電源OFF!
新品のHDDにすること決定なので
今付けてる東芝の同じ「DT01ACA050」を探していると
これが目に留まったのでありました。
Western Digital WD5000AVDS
500GB、5400rpm、ATA300
昨今のマーティーの中でのメーカー嗜好順位は、
Western Digital、東芝、Seagateなのです。
レビューをいくつかみると
・AV機器向けに特化したAV-GPシリーズ
・5400RPMで、低消費電力・低発熱
・HDD・BDレコーダーやTV録画PCなどで
耐久性を維持できるように
ファームウェアがチューニングされている
・今は、この用途のは、PURPLEになっている
とのこと。
スクショは、撮り忘れましたが
そうこうしていると
背面のファンの横に丁度いいスペースがあるのです。
電池ボックスの裏面、端子剥き出しなので
絶縁するシートが必要です。
「コルクシート粘着付」・・・粘着テープじゃな~
確か、PE(ポリエチレン)だったかと
工房では、こんな小さな切れ端も簡単には、捨てません(^^)
斜めカットは、失敗ではありません(^^ゞ
いい感じに入りそうです。
開けました!
でかいカッターナイフで
凡その外形にして~
上のM3ネジを1本外してみます。
上下2本で固定も楽そうです。
内側は、これ
仕切り板というか外殻補強板を留めているネジです。
拡大
このネジが流用できますね~(^^)
先ほどカットしたまな板のプラ板にネジ穴を開けます。
表面に滑り止めのギザギザがあるので、接着にはいいです。
元のネジで取り付けてみます。
ドンピシャです!(^^)!
内側を見ると
プラ板の厚みがあるので、ネジが今一短いですね~
ちょっと長めのネジに換えます。
プラ板なのでツバも大きめです。
この彫刻刀で形を整え、R付けて~
電池ボックスとCR2032を乗せてみます。
電池ボックスの裏側にリード線を半田付けしますが
半田付けの分が盛り上がるので、
まな板プラ板の方に彫刻刀で窪みを掘っております。
半田付け終了
ズームイン
電池ボックスの裏側と接着するので
傷をつけまくります。
前回、電気鉛筆削りのギア修復で使用して
なかなか良かったので、またこれにします(^^)
2連になってて、同時に出せるようになっているのですが
またもや、一方が先に出ようとするので
プランジャーを片方づつ作戦で(^^ゞ
今回は、必要分だけ出すことができました(^^)
爪楊枝で注意深く塗ったつもりですが・・・
拡大してジロジロ見ないように(^^ゞ
3時間後、ツバの広い長いネジで取り付けます。
時計用電池の外付け化、終了であります!(^^)!
あっ!「0:2:16」ってのは、起動してからの時間でした~
今頃気づくマーティーであります~(^^ゞ
東芝の500GBに換装していたので
その時、チェック内容を少し記録しておきます。
やはり、正常に終了できない状態でHDD入換えると、
最初の起動は、これになるのかな?
[スタートメニュー]から[HDD初期化]して
まだ、新品のHDDは、届いてませんが
このまま、東芝のが調子いいので、一旦カバーを被せて
エージング放置してみます。
修理終了も近そうなので、テーブルも片付けております(^^ゞ
1時間ほど別の部屋に行って、戻ってくると
電源がOFFしとる( ゚Д゚)
少し冷静に戻って・・・
[WAIT]ではなくて、時刻表示だな~
電源ボタン押すと、普通に起動しました。
ん?さっきは、無意識に電源OFFして、立ち去ったのかも?
以前、4時間異常なかった実績があるのに
信じられないので、もういちど放置!
やっぱし、30分ほどで電源OFFになり、時刻だけ表示しています。
電源ボタンで普通に起動して
[チャンネル]や[放送切換]しても異常なしです。
換装した時に[HDD初期化]だけやってたので
[設定を出荷時に戻す]します。
電源ボタンを押して起動させます。
デフォルトのまま
ここもデフォルトで
一応、この先も全て記録しておきます。
九州なので
マーティー工房は、福岡地区の~
[次に進む]して
ここから、チャンネル設定です。
一般注意
UHF13~52chまでスキャンしたら~
やっと、地デジが映ります。
現在、一番上のが映っています。
換装後の最初に[HDD初期化]してたら
最初にこれが出ます。
チャンネル設定がRESETされてるので
地デジ映らずブルーバックです。
今は、地デジのケーブルしか繋いでないので
福岡です(^^)
アナログ放送の時代は、マルチパスを避けるために
素子の多いUHFアンテナ+ブースターで「久留米」を受信していました。
修理中は、ネット必要ないので
デフォルトの「利用しない」
CATVスキャンが続いてて、CATV113で終わりです。
時計用電池が正常で時刻も合わせてると
[設定を出荷時に戻す]しても
時刻は、RESETされてなく、調整不要でした。
[設定を出荷時に戻す]しても、ここは、消えないんですね。
換装の秘訣③・・・
「[設定を出荷時に戻す][HDD初期化]の両方をすること」
まっさらのHDDを換装した場合は、
[設定を出荷時に戻す]だけを行っても
[HDD初期化]しないと、こうなっています。
ふ~っ!
HDD換装したら[設定を出荷時に戻す]が原則のようですね~
もう調子はバッチリの様なので
依頼主さんにとって最大の重要事項である
このVHS 120分テープ全域をHDDに録画してみます。
とても分り易いですね~
しかも、全く録画されていません。
既に巻き戻していますが
「テープ頭からダビング」にして「ダビング終了後: 電源入り継続」にして
[ダビング開始]!
再生が始まりました。
2002年のにしては、なかなかの写りです。
左側のオーバーシュートがいかにもアナログーって感じですね~
25秒経過
異状なくVHS⇒HDDに録画されてるようです。
席を外して、30分後、順調かな~?
ありゃ~! 電源落ちてます~(>_<)
HDDに書き込んでいたものの
ファイルの情報を書き込む間もなく電源が落ちたのでしょう。
電源OFFっても、HDD電源は、供給されてて
HDDが急停止するわけではないので、
そこだけが救いであります(~_~)
VHSを巻き戻しました。
開始から16分25秒後に電源が突然落ちたってことですね~
やっぱし、早く新品を着けたいな~
・・・・・あのWestern Digitalが、届きました!
が、ポチッた直後に
あの Western Digital WD5000AVDSは、
プレミアムがついて、楽天での最高値は、これ!
【中古】なのに「未使用・未開封品」ってのも変ですが
他の中古も、2万円台がザラ(゚Д゚;)
マーティーがポチッたのは、もしや、中古どころか偽装品かも?
SeagateのHDDでは、S.M.A.R.T.情報をRESETしたという
偽装新品が出回って、大問題になってるという情報も見つけてしまって
不安は、高まるばかり(@_@)
返品の可能性もあるので
動画で記録しながら、開封~チェックして
最初にCrystalDiskInfo Ver.9.1.1でチェックしたら
電源投入回数:2、使用時間:0
届いて、初の電源投入で「2回」がちと気になりますが
目出度く、新品のようです。
が、S.M.A.R.T.情報をRESETしてる可能性が拭えず
Seagate 300GBのチェックをやった
14, Oct. 2021 ReleasedのVersion 537を使います。
まずは、Quick診断
良好ですね~
どうやら、ホントの新品のご様子(*^^)v
300GB~500GBで3時間ほどかかりますが、
Read Speedのチェックをフル領域でやります。
全て「25」と「100」に入っていました。
いや~、このツール、メチャ時間かかりますが
その分、安心度も高いですね~
が、終了したら、中央の「1.0s」の所に「1」が!
上で、352GBまでは、OKだったわけで
300GB以上の領域は、使わないので支障ないのですが
まあ、これで、正真正銘の新品に決定ですね\(^o^)/
日本に1個しか残ってなかった適正価格の新品だったのかも?
437.8GB辺りで落ち込んでるとこまで追い込んだのですが
では、WD AVDSに換装します。
黄緑が新鮮でいいですね~(^^)
初回の起動は、これでした。
ここのメッセージボックスは、2通りありますが
どちらが出るが、法則が判らず仕舞いです。
つい先を急いで、
[HDD初期化]だけやったら
[チャンネル]押しただけで、フリーズ(>_<)
電源ボタン長押しで、強制終了!
先の健闘で換装した時は、
[設定を出荷時に戻す]しないといけないと分かってたのに
忘れておりましたので、仕切り直しです(^^ゞ
電源ボタン押して起動します。
お馴染みのこれを進めて行って~
念の為、[スタートメニュー]の[設定メニュー]から
[HDD初期化]だけだと、
緑丸部のボタンを押すと、フリーズし易いんです。
[設定を出荷時に戻す]した後は、全く異状は起こりません。
HDDの制御系とどういう関係があるのが見当がつきませんね~
では、VHS⇒HDDの耐久テストやります。
これ以上の完璧なものはないほどのHDDにしたので
筐体も装着して、ネジまで締めての開始であります(*^^)v
VHS⇒HDDダビングにして
[テープ頭からダビング]にして~
終わっても電源OFFしないモード[電源入り継続]にして
[ダビング開始]!
開始から 31分6秒 異状なし(^^)
何も録画されていません(>_<)
上蓋を開けます。
テープが録画されてない部分にきたのかも?と確認しますが
前後は、何の乱れもなく、映像が存在しているのです。
テープを巻き戻すと、
41分55秒の所で、電源が落ちてました(@_@)
どうしても信じられず
どこかで設定を間違えたかな~
ここは、写真を確認しても[電源入り継続]になってましたが
念の為[変更]ボタン押して、選択を上下させてから
[電源入り継続]にして、
2回目の[ダビング開始]!
ダメだ~(>_<)
気まぐれではなく、確実に再現するようです。
VHSを巻き戻すと、さっきよりは、進んでるものの
53分46秒でダウンしております。
新品完璧のWestern Digital WD5000AVDSにしたのに
東芝 500GBでのVHS⇒HDD録画記録 16分を超えただけなのか~(@_@)
VHS⇒HDDを1分ほどダビングすると
ちゃんと記録されてサムネイルができて、再生もできるので
録画機能そのものには、異状ないと判断できます。
ここまでで、解った事と言えば、
HDDを変えると、ダビング耐久時間が変わるってことですね~(~_~)
ちょっと、RD-W301さんから離れて~
先に使ってた、中古の東芝 500GBを外してたので
Quick Scanをやってみると
200GB以内の所で、中央の「1.0s」に「1」が立っています。
やはり、これが、VHS⇒HDDを長くできなかった原因かな~
しかし、そんな所まで書き込みしてないと思うのだが
そもそも、DT01ACA050は、32MBキャッシュ積んでて
地デジ放送のビットレートMax:16Mbpsなので、
皮算用でも 32÷(16÷8)=16sec もキャッシュできるわけで
1sec遅れた所で異状は起こらないはずと考えるのですが・・・
CrystalDiskInfo Ver.9.1.1で診ても
「シークエラーレート」の「生の値」は、オール「0」なのです。
どうも、RD-W301さんの挙動と、HDD診断結果の辻褄が合いませんね~
今日の作業は、止めて
頭を冷やしたいと思います。
ちょっと、ダラダラと思考を書きなぐっております(^^ゞ
そもそも、電源が落ちると云ってきましたが
・電源ボタンは、赤で点灯
・HDDは、回っている
・前面パネルは、時刻を表示している
・電源ボタン押せば、普通に起動して、何のエラーも吐かない
つまり
電源OFFではなく、CPUは、ずっと正常に動いていて、
CPUが、待機状態にさせる指令を出してるのではないかと?
何かの異常でRESET信号を出して、起動時の待機状態に戻った?
どこかジワジワ発熱してサーマルシャットダウンさせたとか?
内部は、メチャクチャ綺麗で、塵一つないので
埃で冷却の通風が悪くなっての発熱は、考え難いです。
もしかして、電源が弱っているのか?
コンデンサの容量抜けでピーク電流に耐えれなくなって
電圧低下を検出してRESET信号を出したのかも?
HDDの比較表を作ってみました。
元のSeagate ⇒ 東芝 ⇒ Western Digital と換装しました。
Power(消費電力)は、Seagateより東芝が低く
たぶん、実際のWestern Digitalは、東芝よりも低いのではないかと。
これまでの「HDDの差」による「RD-W301挙動の差」は、
「Power(消費電力)の差」ではないかと推測するのであります。
右端の東芝2.5inchは、工房にあったので、後ほど登場します(^^)
もしそうなら
消費電力がダントツ低い2.5inchのHDDでやってみるか
或いは、HDDの電源だけ、外部電源から供給してみれば
真相が解るハズです。
そもそも、RD-W301は、ACコンセントに繋ぐだけで
電源OFFの赤ランプ状態でもHDD回ってるんです。
ACコンセントを抜かない限り、停止しません。
ありました!
IDE to USBの変換BOXです。
この電源が使えますね~(^^)
電源のACアダプターは、12V 2.5A
この中の基板上で、12Vから5Vを生成しています。
5V、12V、GNDの
Peripheral Power Connector(DOS/V機用の内部電源コネクタ)なので
SATA電源コネクタへの変換は、このケーブル使います。
更に
中央:DOS/V機用の内部電源コネクタの分岐ケーブル
左:ミノムシクリップのリード線
外部電源の準備が整ったので
RD-W301のHDD WD5000AVDSの電源だけ
外部電源からの供給に配線しました。
ズームイン
全4線がフローティング状態ではまずいので
外部電源のGNDとRD-W301の筐体を
白のミノムシクリップリードで接続しています(水色丸部)
まず、HDDの電源である外部電源を先にONします。
RD-W301のAC電源コードは、抜いた状態です。
IDE to USB変換ボックスの
強烈なブルーのイルミネーションが点灯します。
次にRD-W301にAC電源を供給します。
普通に起動するので、そこは、省略(^^)
早速、VHS⇒HDDダビング耐久テストを始めます。
ダビング開始から16分46秒後の全景Seagateや東芝のは、7200RPMなので、
回ってる振動が、よく判りましたが
このWD5000AVDSは、5400RPMで、メチャクチャ振動が少ないです。
手で触って回ってるのが微かに判る程度。
さすが、低振動を謳ってるだけあります。
黒体反射じゃないので、正確な温度じゃないにしても
40分以上も連続書き込み状態で21.8℃
かなりの低発熱HDDですね~
これは、なかなかいいHDDであります!(^^)!
ちなみに室温です。
築50年以上の木造建築なので、湿度は高め
実は、HDDの温度を測る時にストロボ焚いて
パシッと光った途端、録画停止( ゚Д゚)
更に、その瞬間をもう一枚パシッと光った途端、
テープの巻き戻しが始まり、排出されたのでありました(゚Д゚;)
VHSのテープ最後を検出するフォトダイオードに
ストロボの光が入って、テープが最後だと誤検出したのです。
うかつでした~(^^ゞ
HDDには、ちゃんと記録されてました。45分58秒でした~(^^ゞ
なかなか順調です(^^)
2時間2分7秒
また、最初からやり直しです~(+_+)
今度は、VTR部分の上に段ボール板で遮光しております(^^ゞ
1時間をクリアしました。
順調であります。
もう少しで2時間テープが終わりです。
もうすぐテープも終わりそうです(^^)
ストロボは、焚いておりませんよ(^^ゞ
遂に、テープの最後までダビングできました\(^o^)/
電源が原因であることが確定でありますね~
テープは、自動的に巻き戻しされています。
ちゃんとサムネイルもできています。
2時間3分59秒
HDDのこの辺が最高温度のようですが
2時間の書き込み後、25.0℃ (・。・)
実にいいHDDでありますね~
[本体ユーザー名]と[本体パスワード]が空白なので
[DHCP(自動取得)]を[使う]にして
右下の[接続確認]します。
これが出て
[了解]して
[ソフトウェアのダウンロード]に行きます。
[サーバからのダウンロード開始]します。
IPアドレスとかが入っているので、再度[登録]
もう[放送からの自動ダウンロード]は廃止されてます。
一番下のバージョン、グレーアウトしてて見え難いですが
[ソフトウェアバージョン 04 / MC64]
ちと古いかな~(~_~)
最終確認のポップアップが2回出た後
ダウンロードが始まります。
ダウンロード中は、電源ボタンが赤点灯です。
96%! もうすぐだ!とワクワクしてたらこれは、すぐに消え
公式サイトのアップデートの所を観ると
正常にアップデートできたら、自動的に電源がOFFになる
と載ってるのですが・・・
バージョンの所、案の定、変わってなく
まだ、RD-W301のアップデート情報が載ってるんですがね~
ちなみに、過去の履歴が載っています。
「04 / MC64」とは、下から2番目の事なんだろうな~(~_~)
まあ、VHS⇒HDD⇒DVDへのデジタル化に使う分には
気にしなくていいかな(^^)
それよりも、2つ上のスクショの一番下
「DV連動録画ができない場合がありましたが改善しました」
アップデートできなかったけど
大丈夫なんだろうか?
依頼者さんのデジタルビデオカメラとは、異なりますが
DV連動録画をテストしてみます。
テープは、DV規格のMiniDVです。
i.LINK端子、IEEE1394 4pin、FireWire400
色んな名前を持っています。
VGA画質ですがデジタルなのでキレイです。
MPEG2っぽいですが、時間軸の圧縮はなく、
Motion JPEGみたいな感じなのかな、音声PCMだそうです。
DVカメラを再生モードで停止状態にしておいて
RD-W301のリモコンで
[編集ナビ]-[クイックメニュー]すると
この画面になるので
[DV連動録画]を選択
(前にVHS録画したのを選択してるので項目が沢山でてます)
自動チャプター分割に[日付][シーン切れ目]あるのは
右下メニューは、残ってて、右上に[読込み中]が出ます。
このDVカメラとの連動録画は、異状なしですね~(^^)
DV録画したのは、最右ので、
そこでリモコンの[決定]押すと
分解していきます。
メイン基板の方にコネクタがあるので
DVDドライブを外して
2つの多ピンコネクタを外して電源ユニットからVTR基板へのコネクタを外して
次が、なかなか苦労しまして
この様に、電源ユニットのビスが少ししか上がらず(+_+)
VTR基板を押さえつつ、電源ユニットを引き上げて
やっと擦り抜けました。
最後の1本のビス(中央の)を外して
電源基板とご対面であります。
ガラエポ(ガラスエポキシ)基板で、なかなか豪勢です。
利器率改善用チョーク(左下)がメイントランスよりでかいのは
ちと笑えます。
現在の全景
それにしても、この内部、塵一つないんです(・。・)
HDDの使用時間は、約7000時間、電源投入回数、2500回以上
普通、ファンが付いてると、かなりの埃が内部に積もるんですが
まるでクリーンルームで使われてたかのようなのです。
強烈な空気清浄機を置いてるのだろうか?
引き渡す時に尋ねないと(^^ゞ
半導体がジワジワ弱くなるっては、考えにくいので
弱るとしたら、電解コンデンサの容量抜けか、
上部が膨れることが多いので
ストロボなしで暗めに撮った写真でも確認して
現物もじ~っと確認しますが、怪しい奴は、いないようです。
他にもズーム撮影して確認しましたが
半田クラックは、見当たらず。
というか、ネットには「突然電源が落ちてWAITになる」の報告が
とても多いので、単純な故障ではなさそうです。
基板の型番
PC-POWER-XV81G28DA0000113
検索して見ました。
「G28DA0000113」や「G28DA0000 W301」では、何も出てこず
「G28DA0000」だけだと
TOSHIBA PC−DIG−E301 G28DA0000951−1 基板
東芝製のデジタルビデオレコーダー「RD-E30」用
が、検索リストには、出てきますが
もはや、サイトは存在しません。
「PC-POWER-XV81」だと、ヤフオクに出てまして
動作確認済み 東芝 RD-XV81 電源
PC-POWER-XV81 G28DA0000111
な表題で、外観も極似で
誰~も入札してないので
1,000円+送料 1,500円で落とせるかもですが
「RD-W301」用ではなく「RD-XV81」用だしですね~
ということで、これ以上眺めたり
波形を確認しても、何も得られず、時間の無駄になりそうなので
HDD電源は、外部供給で動作させる改造をやって
この電源さんの負荷を減らしてやれば
このまま頑張ってくれるでしょう。
その前に、2.5inch HDDを内蔵電源だけで試してみます。
東芝2.5inch 1TBを接続して
[設定を出荷状態に戻す]と[HDD初期化]して~
[放送切換][チャンネル]・・・異状なしと!(^^)
5400RPMのHDDなのですが、もうこんな温度に!
先のWD5000AVDSが、いかに凄いかが分ります。
スタンバイ状態に戻ってました。
無事テープの最後まで録画できました!
5V、12Vとも、定格:1.5A
VHSテープを巻き戻すと
50分9秒で、ダメになった様子。
ただ、テープが回った時間よりも少ないですが
10分29秒だけ記録されていました。
この2.5inchのHDDは、
8GBのSSDを搭載したハイブリッドHDDなので
そこに残された分が記録されたのかも?
いずれにせよ、このHDDにしても
内蔵電源だけでは、ダメってことですね~(>_<)
執筆中に気づいたのですが
使用した右端の2.5inch
12Vが不要な分、3.5inchよりも5Vの電流が多いんですね~
どうやら内蔵電源の5Vラインの電流増加で
今回の奇々怪々な現象が起こっているようです。
ということで、
HDD:Western Digital WD5000AVDSにして
電源を外部供給に決定!
というか、もうこの道しか残されてないのであります(^^ゞ
そういえば、工房の宝箱にあれがあった記憶が蘇ってきました。
これが、3個ありました!
確か、外付けUSB I/FのDVD MULTIドライブの内蔵電源を
回収してたものです。
SATA HDDの電源に挿すには
この変換ケーブルだけで済みます(^^)
定格が判らないので
WD5000AVDSの外部電源として接続してみます。
主要パーツの温度を確認します。
VHS⇒HDDダビング中の
5Vラインの電流:0.35A
まあ、簡易型なのでゼロでも±0.03A程度変動しますが
書き込み中でも定格:0.65Aのほぼ半分なんですね~
どうりで発熱が小さいはずだ~
12Vライン 0.25A
こちらも定格:0.5Aの半分だ~(・。・)
このWD5000AVDSは、誠にいい買い物でした!(^^)!
ふと、横を見ると
DVDドライブさんだ~
これの消費電力は、書込みの時、HDDより断然多いハズ(>_<)
これも外部電源にしにしないといけませんね~
ラベルの定格を拡大すると
+5V 1.4A、+12V 1.5A・・・Total 25Wだ~~!
HDDの定格:9.25Wなので約3倍(>_<)
もう少し大きい電源がどっかにあったハズ
別の宝箱をゴソゴソ(^^ゞ
これこれ!(*^^)v
HDDとDVDの書き込みは同時にやらないから
実力値で考えると、どうにか行けるかな~
2Aだと安心なんだが~
これは、もう1個
殻割したのがあるんです(^^)
SATAの電源ケーブルを半田付けして~
一応、負荷としてHDDをつけて12V出力・・・OK
5V出力・・・OK
なことを確認しておきます。
で、これを使おうと思いましたが
この裸のまま使うわけにはいかないし
外殻を作るのは、ちと大変なので
もう一個の奴を殻割りします。
小型ノコギリで中のパーツを気づ付けないようにして~
殻が開きました!
殻割した電源の出力側のブッシュ(右上の)を抜いて
このケーブルを通します
電源についてた元のケーブルは、抜き取って
基板の穴が小さいので
このドリル(Φ1.5)で
穴を広げて
半田付け終了!
下側の殻に入ってもらって~
基板のシルク印刷の
5V:赤、12V:黄、であることを確認
どうも電圧が高い方が赤に思えて間違えそうで(^^ゞ
一旦、上蓋も軽く閉めておきます。
配線用ケーブルやコネクタは、
壊れたATX電源のケーブルが、どっさりあるので
というか、これで電源1台分なのであります。
丁度いいことに
L字型のSATA電源コネクタもありました!
橙色(オレンジ色ともいう)は、3.3V用で
RD-W301では、使わないので、カット!
こういう、ケーブルがゴチャゴチャしたものは、
工房にコネクタ抜きピンがありまして
このコネクタの場合は、円筒のピンを押し込めば
簡単にピンを抜くことができます。
抜いたら、根元をカットして~
4本ともやって
元通りにピン挿せば、キレイになりました。
同様にして
雄雌のケーブルから
GND接続用のケーブルも作っておきます。
HDD、DVDドライブ、GNDケーブルを一体にして
半田付けして、熱収縮チューブを被せて~
このガス式ホットブローで
熱収縮チューブを縮ませます。
ここまでできました!
この右端には、
生の雄ピンがないので
短いのを半田付けして
熱収縮チューブを被せて
雌コネクタと合わせておいて、コネクタカバーに挿入します。
RD-W301に内蔵するケーブルと
外部電源ボックスができました!(^^)!
HDDとDVDドライブを外部電源にして試運転!
続いて、RD-W301のAC電源(左側)をON
異状なく起動して
以前にVHS⇒HDDダビングした分も残っています。
再生テスト・・・異状なしです(^^)
残すは、AC電源を同時に供給させたいので
このコンセントを
背面パネルに付けられると
とても美しい改造にできるのですが
隙間がありません(+_+)
この写真で少し右には、隙間があるのですが
では、電源ユニットの中から
AC電源コードを分岐させるので
また、電源ユニットを開けて、AC電源コードを切断します。
ここは、とても短いので
延長リード線を圧着スリーブで付けます。
普通のカバー付き電工用スリーブで圧着接続します。
ちょっと、近場のホームセンターで
この辺でいいでしょう!
ボール盤の様に簡単には、切削が進みませんが
AC分岐コードも通して、電源ユニットも元に戻して
分岐のACコードの先に、この端子を
カシメて付けて
分岐のAC電源コンセントを付けます。
電流を測定します。
VHS⇒HDDダビングします。
録画が始まったので、電流測定します。
5Vライン:0.70A
12Vライン:0.09A
ヘッドクリーニングのための回転するスポンジなのですが
電源ユニットを元に戻したころには、
ん~ん、これは良さげですね~(^^)
まずは、外形8mmを白ので練習して~(^^)
本番の薄黄を
4mmのポンチをセットして~
こんな感じで押さえて、グリグリ回し切りします。
いいですね~
ゴムブッシュを2種、仕入れてきました(^^)
小さい方に、5V12Vケーブル
大きい方に、AC分岐コード
の切れ端が入ることを確認
外形を溝穴を描いて、型紙を作ります。
どちらも溝穴径Φ8です。
まずは、Φ3でいきます。
1個目終了
次は、Φ4~12まで9段階の
Φ8にするので
広げ過ぎないようにガムテープの目印を巻いておきます。
ん~ん、完璧かな(^^)
これで、バリ取りします。
今一取れませんね~(>_<)
仕上げは、片手で電源ユニットを持ち上げ
でかいドリルビットを手動グリグリっと!
ゴムブッシュを装着
内側
切削屑の掃除は、これでやりました。
このコネクタは、外に出すので
一旦、ピンを抜いて
ちとギチギチのブッシュにしてたので
プラのへらでブッシュを押し込んで、事なきを得ます(^^)
ブッシュ通し作業、終了!
RD-W301の内部の改造は、終了かな(*^^)v
緑で囲んだ所
内部のDVDドライブ用電源コネクタを利用して
外部電源のGNDだけを接続しています。
外部からの電源ケーブルは、
HDDの向こうの隙間に嵌め込んでいます。
外部電源ボックスのAC入力は、
メガネタイプ脱着式になっていて
AC電源ケーブルを短くしております。
このボックスが壊れても簡単に交換できます(*^^)v
ひとまず、AC電源プラグは、一つになった(^^)
プラグが写ってないな~(^^ゞ
筐体を被せて~
ACプラグも1つになって写ってます(^^)
水色テープのは、依頼者さんに見せるための取り除いた内蔵電池
現在、地デジ受信中。
録画はしてませんが、HDDは、常時回っています。
5Vライン:0.65A
12Vライン:0.05A
やけに少ないですね~
HDDスリープしてるのかな?
この位置でのゼロ状態
では、VHSテープを入れて~
何も挟まないと -0.02Aなので
上のは、5V:0.72A、12V:0.11A ですね~
前は、同じVHS⇒HDDダビングでHDDだけの電流が
5V:0.35A、12V:0.25Aだったんだがな~
やっぱ、電流計が簡易型で、真の実効値測定ではないのでしょう。
DVDを再生
左から
5Vライン:0.90A
12Vライン:0.18A
Nonライン:-0.01A
さすがに、DVDドライブは、食いますね~
では、このDVD-Rを焼いてみます。
[する]で進めます。
ここでは、変更できませんが
「ダビングモード:高速そのまま(コピー)」なので
12Vラインの変動が大きいです。
通常は、0.45A辺りの0.5A未満ですが
時々、ビュ~ンと速く回り回転音が大きくなる時
0.84Aまで増えました。
数秒後には、回転音が小さくなり、電流も下がります。
その遷移を繰り返しながら書き込みが進んで行きます。
ディスプレイに[終了]が表示されると
12Vライン:0.10A にガクッと下がります。
12Vライン:0.10A にガクッと下がります。
ファイナライズ中は、
12Vライン:0.45A前後をキープしてますが
最後に0.70A上がり、
終了後は、0.1~0.15Aでした。
かなり安定していました。
HDD⇒DVDへの高速書き込みが
電流的には、最大になる組み合わせと考えられます。
5VラインMax:1.05A
12VラインMax:0.84A
だったので、外部電源の定格
5V:1.5A、12V:1.5Aは、クリアということになるかな(^^)
終わってすぐ
外部電源の蓋を開けて、温度を測ると
ここは、52.6℃
ん~ん、ちと高いな~
こっちは、45.4℃
ここは、45.8℃
総じて、DVDを続けて書込むのは、控えた方がよいですね~
DVDドライブのレーザーダイオードの為にも
・1枚書込みしたら、15分ほど休む
・「高速」ではなく「低速(静音)」の方がいいです
ということで
[HDDパワーモード]を[セーブ]に
設定しておけば、いいでしょう(^^)
外部電源が故障した場合は、これがいいかな(^^)
まあ、届くのに2~3週間ほどかかりますが
「ATX内部機器用 電源アダプター 12V 2A・5V 2A
with Peripheral Power Connector」
330円(45%OFF、送料330円)
所で、電源ユニットを外してる時に気づいたのですが
VTRユニットの赤丸の所
拡大
劣化してボロボロです(>_<)
下に落ちていました。
綿棒にアルコールを浸み込ませて
裏に材質が載ってます。
オレンジの所が「ポリエステル不織布」で硬いしダメですが
ひとまず、ピンセットで取り去りますが
ベトベト状態になってて、ヘッドの方にも付着してます。
ヘッドに当たらないように拭き清掃します。
ここを交換した例がないか、探したけど見つからず(~_~)
スポンジを円筒形に切る手段も思いつかなかったし
クリーニングテープで代用できるので、
放置するしかないかと思ってたら
外部電源の取付が終わった翌日、
この食器洗いスポンジに穴を開けてくれ~と頼まれ
直径12mmのポンチで開けました。
3つ開けた、穴の抜け殻を視てると~
いい感じの触り心地です。
抗菌でAgが入ってますが、イオンなので大丈夫でしょう。
白と薄黄のスポンジが「ポリウレタン」いけそうです(^^)
薄黄の所を0.2mm薄刃のカッターナイフでカット!
さすがに薄刃の切れ味は、凄い!
この部分、待機位置では、ヘッドからかなり離れています。
劣化したスポンジの汚れが、まだ付着しておりますが
回転するので拭き取れないのです~
動作する所を動画で!
この部分は、テープ挿入時と排出時に
一瞬だけ当っています。
当っている状態では、
根本の方が、ヘッドの台座に当たる所まで稼働するので
スポンジの直径は、思ったより小さくていいようです。
真上から
では、スポンジを
目標:8mmでカットしました!
まあ、こんなとこでしょう(^^)
革細工は、やったことないのですが
この他にもありますが、工房にある昔からのポンチコレクション!
上のは、右端の12mmので開けております。
コツは掴めたので~
白と薄黄は、材質同じですが、
何となく薄黄がお似合いかなと(^^ゞ
ポンチの上から叩かないで
回しながら切る感じで巧くいきました。
直径8mmの円柱(下)ができました!
穴開きました!
一発でほぼセンターだ~!(^^)!
ピンセットで装着!
ピッタシです(*^^)v
上から
横から
接触させてみます。
いい感じです(^^)
では、ヘッドクリーニング・スポンジの動作を動画で
テープ挿入時と排出時に一瞬だけ当って回転しています。
全ての修理完了です\(^o^)/
今回は、なかなか勉強になりました。











cG.png)
c.png)
mca.png)



































c.png)








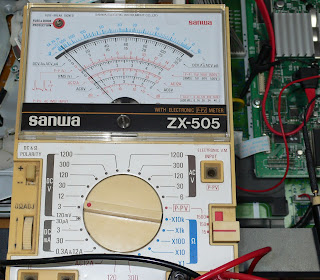


c.png)




c.png)






























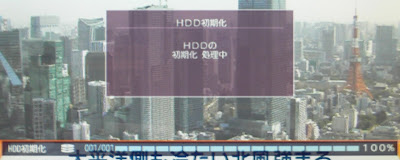


Clean%E5%89%8Dca.png)
c.png)

c.png)













Clean%E5%89%8D%E5%BE%8CacG.png)
Clean%E5%89%8D%E5%BE%8Cacm.png)
cGa.png)
c.png)
ca.png)
cc.png)
c.png)

ca.png)
cc.png)

mc.png)
c.png)








































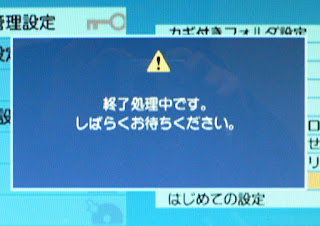

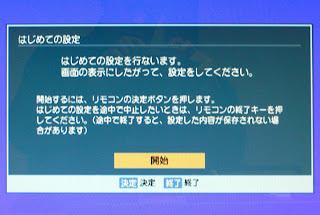





























mc.png)
c.png)
cG.png)
c.png)
Gc.png)
c.png)
Gc.png)
Gc.png)
Gc.png)
Gc.png)






















ca.png)
Gca.png)
c.png)














































c.png)
c.png)
cc.png)



































ca.png)
















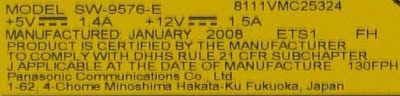



























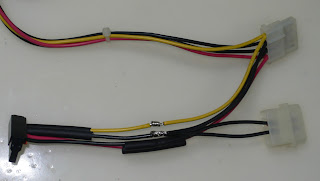










































































c.png)








































