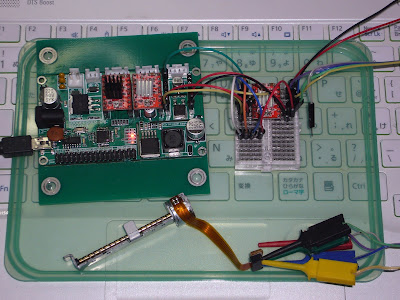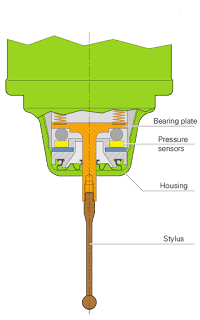なんとか定位置が決まったので、まずは、排気システムが先なのですが
Z軸を可動化させるアイデアが浮かんで、それに興味がいってしまって...
で、アイデアとは、一般的なテーブルを上下させるのではなく
ノズルとレンズ部分を上下に可動させたいと思ったのです。
右往左往の思考パターンをそのまま記録したので長~いです(-_-;)
まずは、宝箱から小型のステッピングモータを探します。
割と古いFAX(おたっくす)を分解して採れたものだったと思います。
候補1:MITSUMI M35SP-12N Datasheetはこれ
・Φ35
・516mA/phase
・トルク:50mN・m、通常の300mN・mから見ると1/6
・7.5°/step
・DC24V仕様、Working DC 21.6~26.4V
ちと大きすぎ。
候補2:MISTUMI M25SP-3Nf Datasheetはこれ
・Φ25
・227mA/phase
・トルク:21mN・m、通常の300mN・mから見ると1/14
・7.5°/step
・DC24V仕様、Working DC 21.6~26.4V
まあ許せるサイズ!
高圧電源モジュールに24Vでてるけど2phaseで約0.5Aはきついかな~
能力半分の0.2~0.3Aで使うとしても別電源だろうなあ~
候補3:仕様不明
裏には「H05 4421BL」とあるだけ
リードスクリューが50mmで大きさ的にはドンピシャなんだけどな~
確か、この5inch CD-ROMドライブを分解して採れたやつで
Φ3のリードスクリューとスライドロッドがあり
とてもスムーズに動くのでこうゆう機構を真似したいのです。
Aliで定格を探していたら、似たやつを見つけて。。。ポチってしまった(-_-;)
Φ15モーター、可動域:53mmで丁度いい
定格は載ってません(T_T)
US$ 2.49/2個
更に探していると
オリジナルは、三共モーターのDPW11というものらしい。
今は、日本電産サンキョーに合併したようで、DPW11のDatasheetはなし。
18°/step、3~6V、10Ω/phase、0.2A っぽい所までわかってきました。
(手持ちのは、16Ω/phaseだった)
トルクが知りたいので、"DPW11"で検索すると、ここに仕様があった!
・ブランド:三共
・0.2A/phase
・18°/step
・巻線抵抗:10Ω/phase(手持ちのは、16Ω/phaseだった)
・固定トルク: 19g-cm(保持トルク)
・スラスト:100gf
「スラスト」とは、スラスト荷重:100gfのことで
軸方向に100gを荷重できるということ(単なる機械的強度でしょう?)
LM8UU:13g なので、7個まで大丈夫ということになる。
たぶん、ノズル部分は、50gいかないと思うので
余裕2倍で摩擦などを考慮しても大丈夫そう!
固定トルクの19g・cmは、
= 1.86326 mN・m
= 190g・mm(中心より1mmの所では)
= 127g・mm(軸径3mmの中心より1.5mmの軸面では)
これは、回転方向に引っ張って保持していれるトルクです。だと思う(-_-;)
= 127g・mm(軸径3mmの中心より1.5mmの軸面では)
これは、回転方向に引っ張って保持していれるトルクです。だと思う(-_-;)
ちょっと高校物理を思い出し、Google先生の指導で計算してみます^^;
軸は、こんな溝です。
1mm位のピッチが欲しいところですが。
溝の傾きをザクッと出して~
かなり単純化して、傾斜を引き上げる時の力で計算します。
μ:摩擦係数とかも、怪しい設定であります(-_-;)
まあ桁まではズレてないと思います^^;
・50gで3.7gf・cm --- 約1/5の能力なので大丈夫そう!
・100gで(摩擦係数0.2として)7.4gf・cm
Max能力の19gf・cmでは、約250gまで保持できることになります。
計算が合ってればの話であります(-_-;)
以上は、Full Step時の能力で、Microstepでは、トルクが下がるので
あまり細かいMicrostepにはしない方がいいのかなあ~?
総重量 50g以下(目標 30g)でHalf Stepにすると
・18°/step、ピッチ 3mm、Half Step だと、0.075mm/step
まあレーザーのZ軸としては、これでもいいかもだけど
・1/8 Microstepにすると、0.01875mm/step
トルクが大丈夫かは、実物で限界まで調整するしかないようです。
軸をM3ネジにできれば、並ネジで0.5mmピッチなので
Half Stepでも0.0125mm/step にはできるのだけど...
気になって先に進めないので、実際に回してみることにします。
CNC2418のWoodpeckerボードを使って
1/16 Microstep、Candle(GRBL Controlソフト)で
24Vは高すぎるので、横に可変電源置いてます。
机上検討じゃなくてKEY上検討。。。失礼しましたm(_ _)m
モータの仕様は、3~6Vのようなのですが、5Vでは、回らず
6.17V、0.054/2phase(0.027A/pahse) 辺りからしか回りません。
A4988の定格 8~35Vに起因する下限のようです。
指で軽くつまむと止まる程度のトルクです。
Woodpeckerは、CNC2418の200step、ピッチ4mm、1/16 Microstepで
800step/mm設定のままです。
CandleからF50で回すと
このステッピングモーターは、20step、3mmピッチなので
200÷20 x 3÷4 x 50 = 375mm/min で回っているはずです。
(1/16 Microstepのままです)
0.1A/phaseにすると、まあまあトルクありそう。
指で軽くつまんでもで大丈夫で、モーターの発熱もほとんどない。
測れないので、キッチン・スケールを指で押して比べての感触では、
200g位の力まで脱調しない感じですが、少し強くつまむと脱調します。
0.2A/phaseにすると300g以上、500gまではいかない感じ
洗濯ばさみをキッチン・スケール上で開くと700~800gなので、
その半分位の感触です。
数十秒回しているとモーターが暖かくなってきます。
Z軸が動く時間は、短時間なので大丈夫そうです。
これは、1/16でもいけそうです!
18°/step、ピッチ 3mm、1/16 Microstep だと、0.009375mm/step!
0.01mm/stepあれば十分です。
ん~ん、キッチン・スケールと指の感触ではよくわからんな~
ならば、実際に釣り上げ実験!
糸をリードスクリューに巻き付けて、先に洗濯ばさみつけて
小さな袋に入れた500円玉を巻き上げます。
6.2V、0.188A/2phase(0.094/phase)、10mm/min!
500円玉 10枚:70g --- ダメかあ、脱調して逆回転します。
7枚:49g --- 巻き上げできました!
上の感触とはちと違いますね~
まあ何となく使えそうなトルクなのでこれで進めることにします。
ちなみに、スペックの「19gf・cm」は、リードスクリュー半径:1cmの時
トルクは、リードスクリューの中心に近づく程、急激に上がります。
中心からの距離に反比例するので、グラフにするとこれです。
1.5mm ⇒ 1mmでは、60gfもトルクが上がることになります。
この辺が計算と実際の違いなのでしょう。
実際は、こんな単純じゃないでしょうが、これ以上突っ込むのは止めておきます。
んで、さっき見つけた、ちと高いけど勢いに乗ってポチッ!(-_-;)
リードスクリューがM3/0.5mmピッチネジなのが魅力、可動域:80mm
DC 4~9V、500mA、18°/step
4ワイヤー:青A+、黒A-、赤B+、黄B-
モーター径:Φ15
US$ 6.86(24% OFF)送料 $2.47
最悪、ダメな場合は、先の候補2のMISTUMI M25SP-3Nf Φ25
のギアをとってカプラーでM3の長いボルトつけようかな。
M3の長いボルトなんて売ってるかな~
これポチッとこっと!
M3 80mm全ネジ棒 US$ 3.08/10本(8% OFF)
ちょっと金属のメインパーツの重量確認です。
Φ3 スライドロッドとM2ボルトとナット。。。27g!
残りは、全部PLAかABSなので50gを超えることはなさそうです。
ロッドは、CD-ROMドライブとか分解して採れたΦ3を使っています。
ブッシュは、アルミダイキャストに埋もれて回収困難なので
それにこのオイルレス・ブッシュをロッド辺り、2個ずつ使っています。
US$ 5.99/20個組
もうちょっと外径が小さいのが欲しかったのですが、探すのに随分苦労した品です。
おっとレンズマウントを忘れてた(-_-;)
レーザーでレンズが熱を持つだろうから、放熱する為にアルミにしたいのです。
赤外線レーザーの検討中に買ってたこのハウジングが余っています。
「808nm laser diode housing 5.6mm laser diode mount
with coated glass lens and adjustable」
 |
| 出所:AliExpress |
 |
| 出所:AliExpress |
これがΦ19で丁度いいんだけど、US$ 22.9 もしたのでもったいないな~
アルミ丸棒をAliExpressで探してみましたが、ここは、
・A6061 Φ18 x 100mmでUS$ 3.52+送料$ 1.45
こっちや
・A6061 Φ16 x 300mmでUS$ 10.80
あっち
・A6061 Φ18 x 300mmでUS$ 11.50
おっ! ミスミのこれが安価ですね~
・A1070 Φ16 x 1000mmで770円
・A1070 Φ18 x 1000mmで870円
・1000番系【純アルミニウム】
純度が高いので導電性・熱伝導性・耐蝕性がいいが、
強度が低く、粘り気があるので加工に注意。
A1070は、純度 99.7%以上
・6000番系【AL-Mg-Si系合金】
Si、Mgとの合金で、Mgだけの5000番系より強度・耐食性に優れる。
A6061は、Cuも添加され、熱処理で硬度が上がる。
・切削加工は、5000番系【AL-Mg系合金】がやり易いとのこと。
1000番系の方が高価な気がしますが...
ということで、ミスミでしょう!
1mもいらんけどな~、と、注文しようとしたら
閃きました!
これこれ!
フレキシブルカプラー!
測ってみると、Φ19!これこれ!
フレキシブルカプラー!
随分前に買ってた「5 x 8」US$ 0.98(5% OFF)
片側は、Φ5側なのでΦ8に広げて、8 x 8にすればいい、これに決まりです!
重さは、15g
さっきのと合わせると~
27+15 = 42g
ん~ん、50gちょっと超えそう(T_T)
と、ここでCNCで削りたくなったので
フレキシブルカプラーでレンズマウント作り、前回の日誌に飛びます。
CNCに夢中になり記録のまとめをサボって順序が逆になったわけです(-_-;)
完成~! レンズはまだ付けてないです。
大凡の主要パーツが決まったので
やっとFusion360で設計に入るわけであります^^;
既に進んではいますが、過去になく複雑になり、なかなか大変です(-_-;)
PARTⅡに続きます。